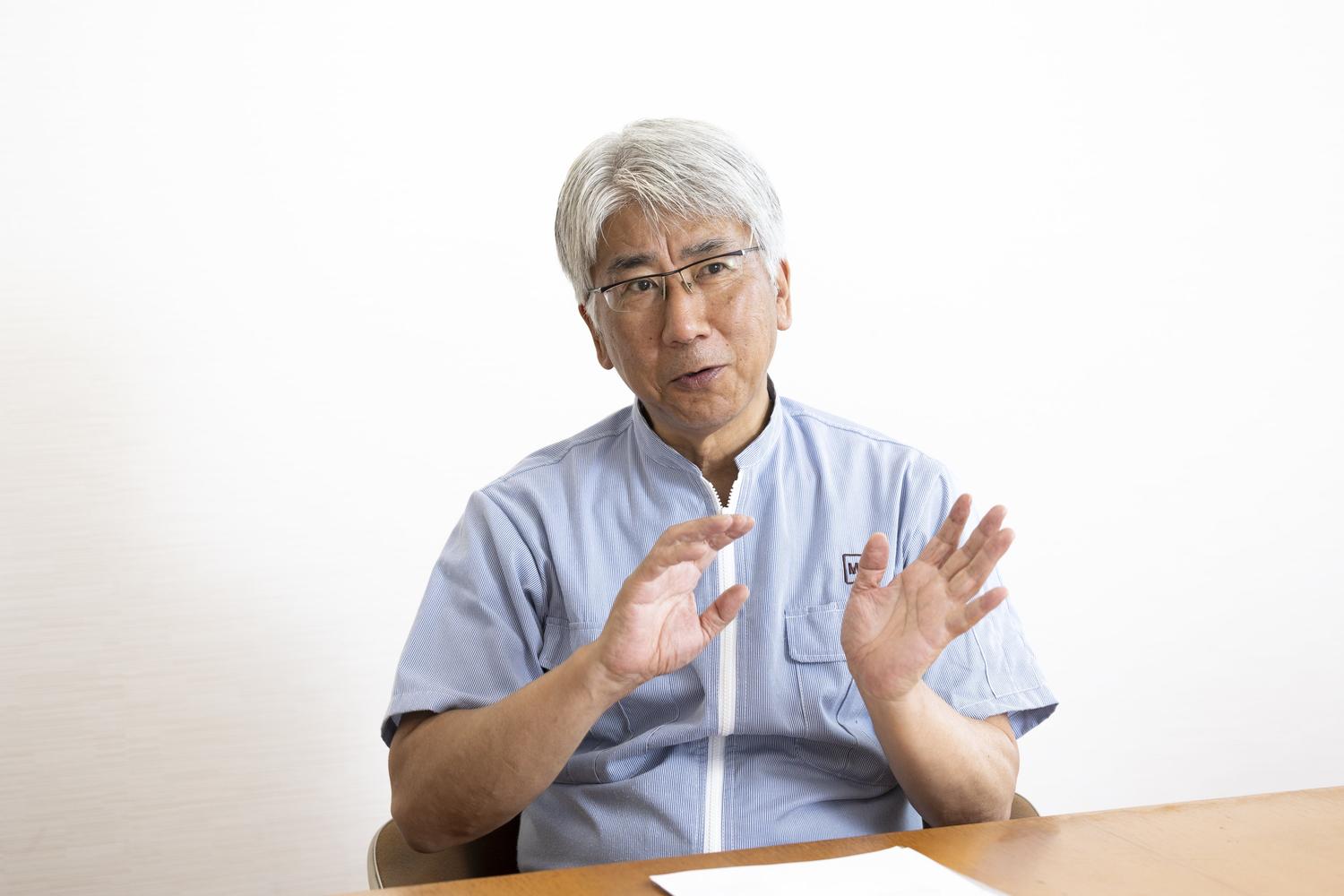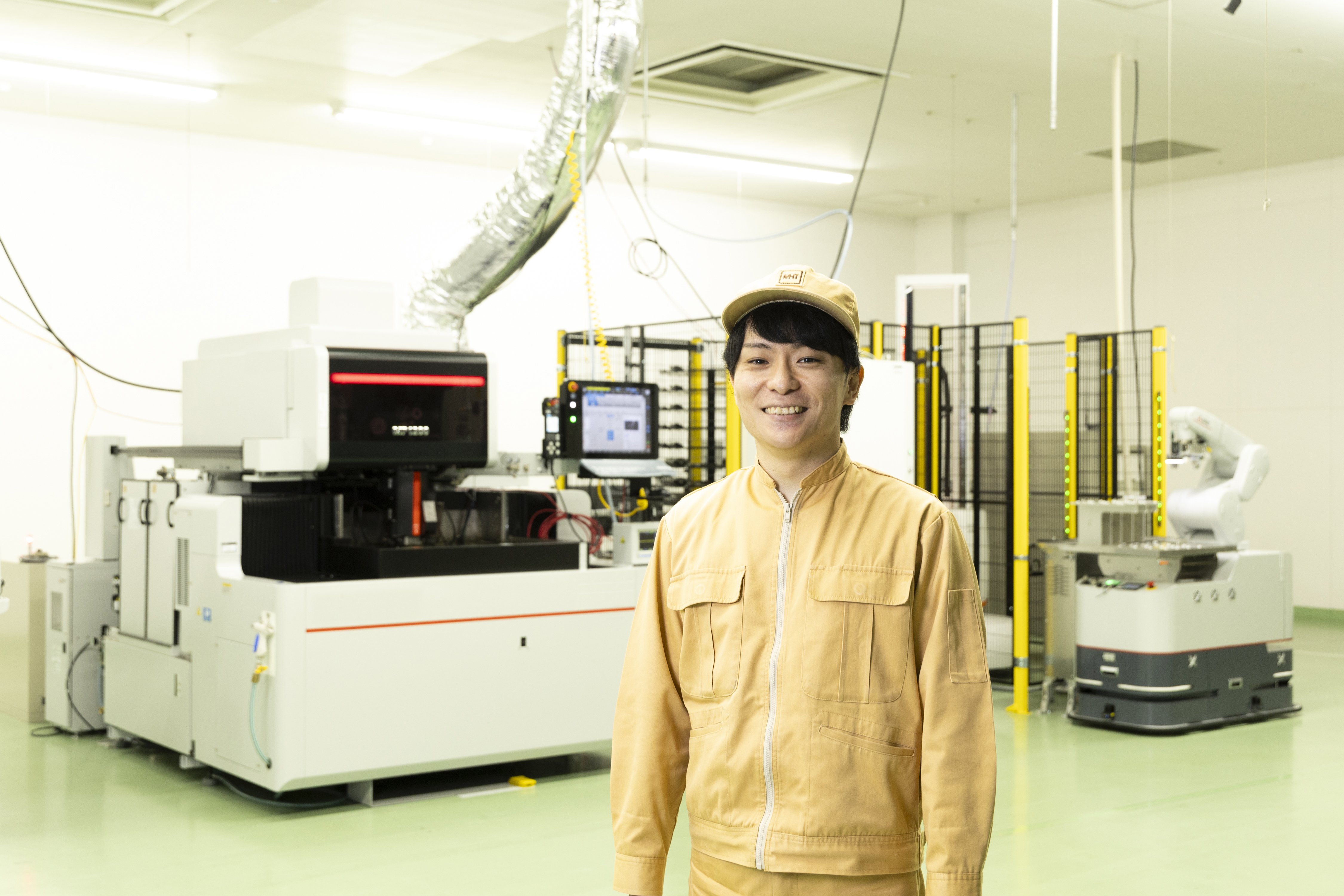ベテランと若手が組み
プロジェクトがスタート
H
2017年に、三井ハイテックのモーターコアを採用されている自動車メーカーの方から、「ヨーロッパで現地生産できないか」と要請を受けたことがきっかけでした。当時、三井ハイテックの海外生産拠点は北米とアジアだけで、ヨーロッパにはありませんでした。
ヨーロッパのどの場所に生産拠点を設立するかで、採算性は大きく変わってきます。土地・建物の取得コストから始まり、人件費やエネルギーコスト、材料の調達や流通にかかるコスト、政府の税制・補助金や法的規制の有無など……。複数の候補地において、これらのコストがどのぐらいになるのか、正確にシミュレーションすることが重要です。その調査と試算を担当したのが、私たち3人でした。
私は要請があったメーカーの営業を担当していました。約35年前の入社以来、さまざまな事業部を経験して、国内外含めて十数回転勤し、海外赴任の経験もあったことから、声がかかりました。現地で、人件費や政府の税制といった情報を収集するのが私の主な任務でした。
Y
Hさんが現地で収集した情報を、別の情報源を使って精査した上で、製品原価をシミュレーションするのが、本社にいる私とMさんの役割でした。
当時の私は入社5年目。モーターコア事業企画統括部事業企画部の事業企画グループに所属し、モーターコアの原価試算や、海外グループ会社の原価管理や予算管理を担当していました。
ただ、海外拠点の原価シミュレーションをしたことはあったものの、ヨーロッパに関してはまったく経験がありませんでした。国が違えば、原価を左右する要素も異なってきます。その要素を漏れなく見つけられるのか、それらについて本当に正確な数字が算出できるのか、正直不安でした。
M
不安だったのは私も同じです。私は入社3年目で、Yさんに原価試算の方法を教えてもらいながら、一緒に市場調査をしていました。これまでの業務は与えられた情報をもとに決まった方法で試算することが多く、自分たちで一から考えるのは、これが初めてでした。
H
私も国内の生産拠点の用地を探す仕事に携わったことはありましたが、海外の用地は初めて。しかも調査に与えられた期間は6カ月程度しかありません。私を含め全員が不安を抱えておりましたが、のんびりしている時間はなかったので、とにかく動き出しました。

未知のヨーロッパ
正確な情報収集に苦労する

H
まずは、ヨーロッパ各国の複数の候補地について、調査を開始しました。
私は、東京にある各国の大使館にアクセスして、工業団地や税制などの情報を集めた後、一人で月1回現地に赴き、商社のサポートを受けながら、日本大使館や関係省庁などを訪問したり、工業団地を視察したりして、情報を集めました。
M
一方で私は、BEVやHEVといった環境対応車がヨーロッパでどの程度売れているのか、また今後どのぐらい市場が成長していくのかを予測しました。契約している情報機関の情報だけではなく、銀行からも情報をいただいて、複数パターンから市場予測を判断していました。
Y
私は、ヨーロッパの工場でつくるモーターコア1つあたりの生産コストをシミュレーションしました。その試算結果と、Hさんがまとめた地域ごとの労働条件や補助金などの情報をベースに、Mさんに工場全体コスト試算してもらいました。
H
何度も日本とヨーロッパを往復していたので私も大変でしたが、若い二人の方がもっと苦労していたと思います。期限が決まっているなか、経営判断を左右する数字を試算しなければなりませんからね。
Y
まず苦労したのが、試算に必要な情報を漏れなく集めることです。
ヨーロッパは、日本とは労務条件費や人件費なども違いますし、材料の単価も拠点によって異なります。そういう拠点ごとの情報が手に入らないと、正確な試算ができないのです。
そこで営業部門などと連携しながら情報を収集したのですが、これが難航しました。
M
新しい工場をつくるとなれば製造、営業、技術などさまざまな部門が関わってきますが、社内でも多くの部門があり、誰に聞けば欲しい情報が手に入るのかが分かりませんでした。そこで、知っていそうな方にとりあえず聞いてみて、知らないということであれば、次の方に聞いて……、というのを1カ月ぐらい繰り返しました。
Y
社内の方に聞いても分からなければ、インターネットで調べたり外部の方に聞いたりしましたが、それでも分からない情報がありました。すでに生産している北米工場の情報もヒントにして、予測値をなんとか割り出しました。
30以上の候補地に対するシミュレーションを
約3カ月間ですべて完了
H
候補地は1つだけではありません。ポーランド、チェコ、ドイツの3カ国に絞りましたが、複数の候補地があり、全部合わせると30以上あったのではないでしょうか。
M
しかも、1つの候補地の試算が終わったら、また新たな候補地が出てくるといった状況で……。やっと残りが2カ所になったと思ったら、いつの間にか5カ所に増えていることもあり、Hさんから送られてくるレポートを見ながらしょんぼりしていました(笑)。
Y
私たちはこの仕事を通常業務と並行して行っていたので、時間のやりくりにも苦労しました。私も途中で心が折れそうでした(笑)。
M
30カ所のシミュレーションを約3カ月で行った後、ポーランドに絞り、そのなかで5カ所を綿密にシミュレーションしました。30カ所は概算でしたが、最終候補の5カ所はさらなる正確さが求められたので、強いプレッシャーを感じました。
H
「こんなことまで試算するのか」と思うぐらい細かな項目まで網羅していて、驚きました。ベストな場所を選定できたのは、そんな二人の頑張りが大きかったと思います。
Y
私とMさんは試算までで、その後の工場建設プロジェクトには関わっていないのですが、2021年にポーランドの工場が稼働した時は、やはり嬉しかったですね。
M
試算をしていた時はずっと日本にいたのですが、近いうちにポーランド工場を見学できそうなので、すごく楽しみにしています。

経営会議で新たな視点に気づき
自分たちの仕事に活かす
M
今回、ヨーロッパ拠点のプロジェクトに携わったことで、多くのことを学ぶことができました。1つは、営業や製造、技術など、事業部全体の業務の流れを知ることができたことです。それ以前は自分の部署に関係していることしか知らなかったのですが、多様な部署の方と接することで、部署同士のつながりや、製品がどのような流れで生産されているのか理解できました。2023年に事業管理の部署に異動し、24年からはマネジャーとして、モーターコア事業の業績取りまとめや会議・業務を円滑に進めるための仕事をしているのですが、事業部全体の業務の流れを学ばなければ、今の仕事はできていなかったと思います。
Y
本プロジェクトで、原価シミュレーションの報告をするため経営会議に初めて出席したのですが、経営層の視点を知ることができ、非常に勉強になりました。経営層は1つの業務範囲だけでなく、製造も管理も営業も見なければならないので、多角的な視点を持っています。
その視点に触れたことが、後に携わったメキシコ工場のコスト試算に活かすことができました。さまざまな部署の観点を知ることで、「こういうコストの抜け漏れがある」ということに気づけるようになったのです。より精度の高いコストシミュレーションにつながったと感じています。
M
Yさんがおっしゃるとおり、経営会議に出席したことで、本当に見る視点が違うことを思い知らされました。とくにリスクに関する考え方が印象に残っています。それ以来、自分が担当している業務でも、起こり得るリスクを考えて、それらに対してどう対応していくのかという、リスクヘッジを考えられるようになりました。
Y
これまでは他の部署との関りが少なかったので、連携するのも得意ではありませんでしたが、このプロジェクトに参加して苦手意識が弱まりました。海外のグループ会社と定期的にミーティングを行う際、現地スタッフとやり取りすることにも慣れました。今後は海外のグループ会社と関わりを強めて、英語力を活かせる仕事ができればと考えています。
M
私はもともと活動的なタイプではなく、仕事でも「指示待ち」のところがあったのですが、プロジェクトに参加してからは、指示を待たずに自分で考えて、提案するようになりました。働き方が別人のように変わったと自分では思っています(笑)。
今回のプロジェクトでは、モーターコア事業部だけでなく、全社的に取り組まないと解決できない問題がいくつかあると気づきました。例えば、情報共有の方法はその1つです。こうした課題を、本社の管理部門などとも連携し、改善していきたいと考えています。すでに取り組んでいる活動があるので、それをもっと広げていくことから始めていこうと思っています。